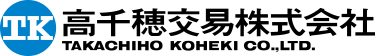RFIDとNFCの違いは?導入前に押さえたい基本と選び方のポイント
業務効率化や非接触型の運用ニーズが高まるなか、RFID*1やNFC*2の導入を検討する企業が増えています。しかし、「どちらを選ぶべきか」「何がどう違うのか」といった疑問を抱えたままでは、適切な判断が難しいのも事実です。読み取り方式や通信距離、導入コスト、運用のしやすさなど、両者には明確な違いがあります。
この記事では、RFIDとNFCの技術的な違いや、それぞれの周波数帯・活用シーンをわかりやすく整理し、導入前に押さえておくべき選定ポイントを解説します。現場の課題に即した最適な選択を行うための判断材料として、お役立ていただければ幸いです。
*1 無線周波数を用いてICタグの情報を非接触で読み取る技術 *2 13.56MHz帯を使った近距離無線通信技術
RFIDとNFCとの違い
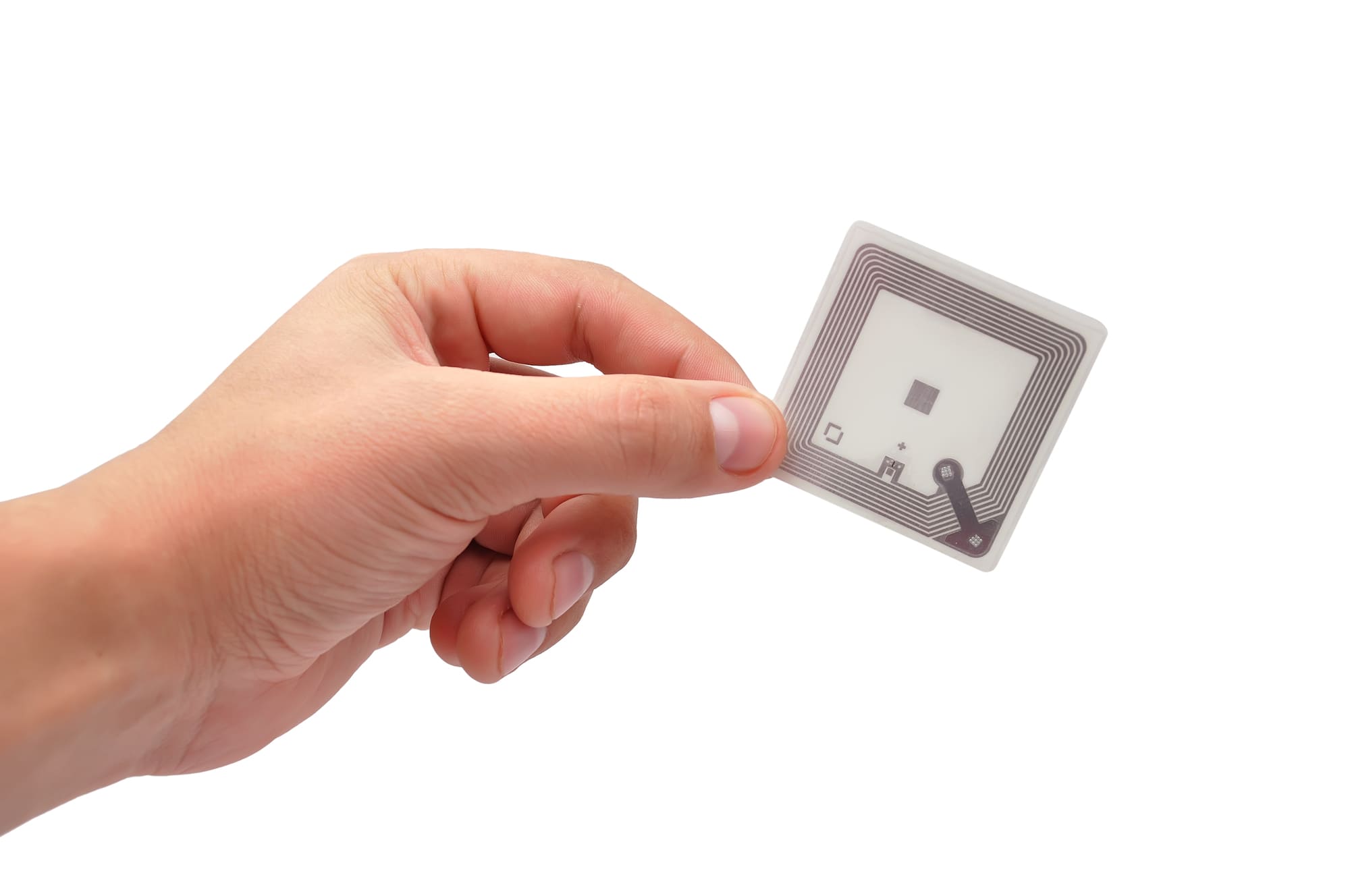
RFIDとNFCはいずれも無線通信によって情報をやり取りする技術ですが、その仕組みや用途には明確な違いがあります。どちらも非接触での認証やデータ取得を可能にする一方で、通信距離や読み取り方式、適した活用シーンが異なるため、混同せずに理解することが重要です。ここでは、両者の基本的な違いについて、実務での導入を見据えた視点から解説します。
RFIDの特徴
RFID(Radio Frequency Identification)は、無線周波数を用いてICタグの情報を非接触で読み取る自動認識技術です。タグに内蔵されたICチップとアンテナから情報を専用のリーダーで取得することで、物理的な接触や視認を必要とせずにデータの読み取りが行えます。
近年では、物流・小売・製造などさまざまな分野で、在庫管理や資産管理の効率化を目的として広く導入されています。
RFIDの主な特徴は、以下のとおりです。
- 利用する周波数帯(LF帯・HF帯・UHF帯など)によって通信距離や用途が異なる
- UHF帯は複数タグの一括読み取りが可能で、棚卸や入出庫作業の効率化に最適
- 書き込み機能を備えたタグも多く、再利用やデータ更新に柔軟に対応できる
ただし、読み取り精度は周囲の環境によって影響を受ける場合があります。導入時には、アンテナの設置場所や遮蔽物の有無など、現場の状況に応じた調整が欠かせません。
参考:RFIDとは?基礎からメリット・デメリット、導入事例まで解説
NFCの特徴
NFC(Near Field Communication)は、13.56MHzの周波数を利用した近距離無線通信技術で、RFIDの一種に分類されます。通信距離はおよそ5mm〜50cmと非常に短く、タグ1つに対して1つのリーダーを使用する読み取り方式が基本です。この特性により、意図的で確実な操作が求められるシーンに適しています。
スマートフォンやICカードなどにも組み込まれており、以下のような用途で広く活用されています。
- 個人認証
- キャッシュレス決済
- 入退室管理など、人とシステムを結ぶインターフェース
通信モードは主に機器間通信(P2P)・リーダー/ライター方式・カードエミュレーションの3つがあるため、それぞれの場面で柔軟に使い分けることができます。
RFIDと比べると読み取り範囲は限定されますが、そのぶんユーザー操作性の高さやセキュリティ面での強みが際立ちます。特に、情報の精密な制御が求められるシーンでは、NFCが有力な選択肢となるでしょう。
RFIDの周波数の種類

RFIDでは、使用する無線周波数帯によって、通信距離や読み取りの安定性、そして環境への耐性が大きく変わります。目的や設置環境に応じて、最適な周波数帯を選定することが重要です。
通信方式は主に、近距離通信に適した「電磁誘導方式」と中〜長距離通信に用いられる「電波方式」の二種類があります。
電磁誘導方式はコイル型アンテナを使ってタグとリーダーの間に磁界を発生させ、近距離で通信を行う仕組みです。一方、電波方式では平板型アンテナを使用し、電波によってデータと電力をタグとリーダーの間でやり取りします。
通信方式と周波数帯の違いを正しく理解しておくことで、導入する現場に最適なRFIDシステムを選びやすくなります。ここからは、LF帯からマイクロ波帯まで、それぞれの特徴と代表的な活用例を順にご紹介します。
LF帯(低周波:~135 kHz)
LF帯(Low Frequency)は135 kHz以下の周波数帯で、電磁誘導方式で通信します。読み取り距離はおおむね数十センチから1 m程度と短めですが、金属や水分の影響を受けにくく、堅牢な通信が可能です。多くのシステムでは125 kHzが採用され、134 kHzを用いる例もあります。
通信速度は比較的遅いものの、耐環境性の高さが強みとされ、安全で安定した運用が求められる現場に向いています。世界各地域で使用可能な周波数帯であることも、導入ハードルを低くする要因のひとつです。
ペット・家畜管理や車のスマートキー(キーレスエントリー)など、湿気や金属のある環境下でも安定した識別が必要な場面で用いられます。
HF帯(高周波:13.56 MHz)
HF帯(High Frequency)は、13.56 MHzの周波数を使用する高周波の通信方式で、LF帯と同様に電磁誘導方式を採用しています。通信距離は約5mm〜50cmと短く、非接触での近距離通信に適しています。
このHF帯は、NFC(Near Field Communication)にも使われており、日常生活で最も身近なRFID技術のひとつです。通信範囲が限定されている分、意図的な操作が求められるシーンに向いています。
HF帯の特徴を活かした主な用途は次のとおりです。
- 社員証や学生証などの個人認証
- 会員証やポイントカード
- 交通系ICカード(例:Suica、PASMO)
- 図書館の貸出管理
- 医療現場での患者識別
また、HF帯はLF帯に比べて小型・薄型のタグを実現しやすく、カード型やシール型など、柔軟な形状への展開が可能です。金属や湿気の影響も比較的受けにくいため、安定した読み取りが求められる現場でも効果を発揮します。
通信規格としては、ISO/IEC 14443やISO/IEC 15693といった国際標準に準拠しており、異なる機器やメーカー間でも高い互換性を持つのも強みです。
さらに、通信速度はLF帯よりも高速で、ユーザーにとってスムーズな操作性を提供します。セキュリティ性能も高めであり、機器認証や個人データの取り扱いにも安心して使用できる方式です。
UHF帯(超高周波:860〜960 MHz)
UHF帯(Ultra High Frequency)は、860〜960MHzの周波数を使用するRFID通信方式で、日本国内では主に920MHz帯が利用されています。通信方式は電波方式で、LF帯・HF帯に比べて長距離の通信が可能です。
通信距離は最大で約10メートルにおよび、複数のタグを同時に読み取れるという特徴があります。
このため、以下のようなシーンでの活用に適しています。
- 倉庫や物流センターでの在庫管理
- 小売店舗での商品棚卸
- 工場での資産トラッキング
- 検品・入出荷業務の効率化
UHF帯は、RFID技術の中でも一括読み取り性能が特に高く、作業時間の短縮や人手削減につながることから、業務改善の現場で多く採用されています。小売店舗の商品タグとして使用されることも多く、消費者にも比較的身近なRFID技術といえるでしょう。
一方で、UHF帯は金属や水分の影響を受けやすいという弱点があります。そのため、使用するタグの種類や設置場所には十分な検討が必要です。環境に応じたタグの選定やリーダーの配置を最適化することで、読み取り精度を安定させることができます。
マイクロ波帯(2.45 GHz)
マイクロ波帯(2.45 GHz)は、電子レンジや無線LANなどと同じ周波数帯を利用するRFID通信方式で、電波方式に分類されます。通信距離は数メートル程度と比較的広く、直進性が高いという特性を持っています。
このため、タグの位置を限定的に正確に読み取りたい場面に適しており、以下のような用途で活用されています。
- 書類や資料のピンポイントなトラッキング
- 棚の特定段への配置確認
- 限られた範囲内での物品検出
- ラック管理や設備の通過確認
一方で、マイクロ波帯は金属や水分、遮蔽物の影響を受けやすいという弱点があります。これにより、読み取りが不安定になったり、通信距離が短くなったりする可能性があるため、導入時には設置環境の事前調査と電波干渉の考慮が欠かせません。
また、電波の指向性が強いため、広範囲の一括読み取りには不向きですが、あらかじめタグの位置が限定されているような管理用途においては、高い精度で情報を取得できます。
NFCの用途別の種類

RFIDの一規格であるNFCの正式名称「Near Field Communication」は、その名の通り、数センチ程度の近距離で通信することを前提とした技術です。スマートフォンとの連携や個人認証、入退室管理、イベントでの本人確認、さらには工場の工程管理など、人と機器のあいだで確実にデータをやり取りする場面に適しています。
NFCには、国際標準に基づく複数の通信方式(プロトコル)が存在します。代表的なものとしては、「Type-A」「Type-B」「Type-F(通称:FeliCa)」「Type-V」があり、それぞれ通信方式や活用シーンが異なります。
どのタイプを採用するかは、目的や運用環境に応じて判断する必要があります。ここからは、それぞれのTypeの特徴と活用分野について詳しく見ていきましょう。
Type-A
Type-Aは、国際標準規格であるISO/IEC 14443およびISO/IEC 18092に準拠した、NFCの代表的な通信方式のひとつです。読み取り速度は標準的ですが、NFCデバイス間での通信やデータのやり取りが可能で、高い互換性と低コストを両立している点が特徴です。このため、世界的に広く普及しています。
主な活用例としては、以下のようなものがあります。
- 社員証・IDカードによる個人認証
- NFC対応スマートフォンとのデータ連携
- ポイントカードや会員証
- ホテルのルームキーなどのアクセス制御
セキュリティ性能は平均的ですが、汎用性が高く、さまざまな用途に適応しやすいバランスのとれた方式と言えるでしょう。
Type-B
Type-Bは、Type-Aと同様にISO/IEC 14443に準拠したNFCの通信方式ですが、電気的な通信仕様が異なる点が特徴です。主に、高いセキュリティ性能が求められる分野で使用されています。
代表的な活用例としては、以下のようなものがあります。
- eパスポート(IC旅券)
- マイナンバーカード、運転免許証などの公的ID
- クレジットカードのタッチ決済
これらの用途では、暗号化通信の強さと信頼性の高さが重視されており、Type-Bが適した選択となります。
Type-Aに比べて対応機器がやや限られる傾向にありますが、情報の正確性や改ざん防止が求められる場面において高い評価を受けている方式です。
Type-F(FeliCa)
Type-Fは、ソニーが開発した「FeliCa」規格に基づくNFCの通信方式で、**ISO/IEC 18092(NFC-F)**として国際標準化されています。日本国内では特に普及しており、**交通系ICカード(例:Suica、PASMO)や電子マネー(楽天Edy、WAONなど)**といった非接触型決済に広く利用されています。
通信速度は最大424kbpsと高速で、認証処理が瞬時に完了することから、スムーズでストレスのない利用体験を実現します。この特性により、混雑時の改札通過やスピードが求められるレジ決済などでも安定したパフォーマンスを発揮します。
FeliCaは、日本市場において最も身近なNFC規格のひとつであり、公共交通機関・流通・エンターテインメント分野など、日常生活に密接したさまざまなシーンで活用されている方式です。
Type-V
Type-Vは、ISO/IEC 15693に準拠したNFCの通信方式で、「NFC-V(vicinity)」とも呼ばれます。他のNFC規格と比較して通信距離が長く、おおよそ1メートル前後までの読み取りが可能な点が特徴です。UHF帯に近い使用感を持ちながらも、HF帯の安定性と近距離通信の特性をあわせ持っています。
主に以下のようなシーンで活用されています。
- 工場や倉庫における棚卸管理
- 設備の点検履歴やメンテナンス記録の管理
- 資産の個別追跡(トラッキング)
- 厳しい環境下での耐久性を求める運用
Type-Vは、大容量のデータ保存が可能で、データの破損リスクも比較的低いとされています。このため、金属や湿気の多い現場などでも安定した運用が期待できる通信方式です。
NFCの中でも、特に産業用途や物流領域への実装を前提に設計された規格であり、現場の業務プロセスを支えるための選択肢として有効といえます。
高千穂交易株式会社が提案するRFID・NFCの活用事例

これまで、RFIDとNFCの違いや各周波数帯の特性について解説してきました。では実際の現場では、それぞれの技術がどのように選ばれ、活用されているのでしょうか。
当社では、製造・物流・小売・イベント運営など、さまざまな業種・業態において培った経験をもとに、現場の課題や運用目的に応じた最適な技術選定と導入支援を行っています。特に、RFID(UHF帯)とNFC(HF帯)の機能特性を見極め、「どこで・何に・どのように使うべきか」を現場目線でご提案することを強みとしています。
ここでは、実際にご支援した導入事例をもとに、現場での活用イメージや導入効果をご紹介します。
RFID(UHF帯)を活用して検品や棚卸やレジ会計を効率化
高千穂交易株式会社では、RFID(UHF帯)の特性を活かし、店舗や物流拠点における業務の省力化・スピード化を支援しています。なかでも、アパレル店舗や物流センターでの検品・棚卸・レジ対応といった工程で大きな効果を発揮する点が強みです。
たとえばアパレル業界では、商品に取り付けたRFIDタグ(UHF帯)を専用リーダーで一括読み取りすることで、数秒で会計処理が完了する無人レジの実装が可能となります。また、棚卸や出荷時の検品作業も、一人で・短時間に・正確に進めることができ、人手不足の解消や業務標準化にもつながるでしょう。
これにより、作業時間の大幅な削減に加え、ヒューマンエラーの防止や顧客満足度の向上といった副次的な成果も期待できます。RFID(UHF帯)は、単なる省力化ツールにとどまらず、業務プロセスそのものを見直す契機となる技術として、多くの現場で採用が進んでいます。
NFC(HF帯)を活用した入退室管理システム
RFID(UHF帯)が広範囲での一括認識に強みを持つ一方で、NFC(HF帯)は「人と設備の確実な認証」を得意とする技術です。
高千穂交易株式会社では、この特性を活かし、NFC対応の入退室管理システムを各種施設に提案・導入しています。
例えば、NFCを搭載した社員証やスマートフォンを使用すれば、扉のリーダーにタッチするだけで認証が完了します。アクセス制限を設けたエリアへの入退室管理や、個人ごとの履歴記録も可能となり、セキュリティの強化と運用の効率化を同時に実現できます。
また、クラウドと連携したシステム構成により、管理者側の業務負担を軽減できる点も大きな特長です。出社・退勤データの可視化や緊急時の在室確認といったBCP(事業継続計画)対策にも対応しており、柔軟な働き方やフレキシブルなオフィス運用を支える基盤としても有効です。
導入規模やレイアウトに応じてシステムの構成を柔軟にカスタマイズできるため、小規模オフィスから大規模施設まで幅広く対応が可能です。
NFC(HF帯)を活用したイベント運営
NFCは「人と設備の確実な認証」が求められる場面で強みを発揮する技術であり、イベント運営の現場でも幅広く活用されています。とくに、参加者の利便性向上と運営効率の両立を実現する手段として注目を集めています。
たとえば、入退場管理にNFCタグを活用することで、参加者はタグをリーダーにかざすだけでスムーズに出入り可能です。これにより、受付やゲートの混雑を緩和しつつ、セキュリティレベルの向上も図れます。
さらに、事前に電子マネーをチャージしたNFCタグを配布すれば、会場内での飲食やグッズ購入などにおいてキャッシュレス決済が可能となり、財布を持ち歩く必要もありません。スピーディーな決済により、滞留時間の短縮と購買体験の向上にもつながります。
そのほか、会場内にNFCリーダーを複数設置し、スタンプラリー形式でタグを読み取る仕組みを導入すれば、来場者の回遊を促進する仕掛けとしても活用できます。訴求エリアへの誘導やイベント全体の回遊率向上、参加者満足度の強化など、多面的な効果が期待されます。
RFID(UHF帯)で実現する製造現場のスマート工程管理
RFID(UHF帯)を活用した工程管理は、製造現場における「見える化」と業務効率の向上を同時に実現する手法として、近年注目を集めています。とくに、大量生産を担う現場では、部品の状態や位置、生産の進捗をリアルタイムで把握することが不可欠です。
部品や製品にRFIDタグ(UHF帯)を取り付けておくことで、生産日時・ロット情報・製造工程などを即座に読み取ることが可能になります。これにより、不良品の発生原因の追跡やトレーサビリティ強化に貢献します。
また、設備メンテナンスの現場では、RFIDタグを使って機器の点検履歴や故障情報を管理することで、作業の正確性とスピードが向上します。結果として、ダウンタイムの最小化や保全業務の平準化にもつながるのです。
このように、RFIDによって得られた情報を現場で即座に共有・活用できる体制を構築することで、製造業における品質と生産性の両立、そしてDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速を力強く後押しします。
導入コストや運用面のポイント
RFIDやNFCを現場に導入する際は、初期費用だけでなく、運用面も含めた総合的な視点での検討が求められます。特に、タグやリーダーといった機器のコストに加え、基幹システムとの連携や設置工事、運用体制の整備など、さまざまな費用が発生します。
たとえば、RFID(UHF帯)は、複数のタグを一括で読み取れる点が大きな利点です。大規模な現場や物流工程の自動化に適している一方で、タグの単価は数量や耐久性の要件によって変動し、読み取り機器やソフトウェア、既存システムとの連携構築も含めると、数十万円から数百万円の初期投資が必要になるケースもあります。
一方で、NFC(HF帯)は通信距離が短いため、管理対象が限られたシーンでの活用に適しています。NFCタグは比較的低価格で、スマートフォンをリーダーとして利用できるため、小規模な導入であれば初期費用を抑えやすい点が特徴です。ただし、管理エリアの広さによっては、読み取りポイントの増設が必要になることもあります。
どちらの技術を選ぶにしても、運用の目的とスケールに応じた適切な選定が、導入効果を大きく左右します。特に現場の環境や作業フローに即した設計ができていないと、導入後の効率化が十分に発揮されない可能性もあるため注意が必要です。
高千穂交易株式会社では、導入前の現場診断から機器選定、システム連携、運用後のサポートまでを一貫してご提供しています。長年の実績とノウハウをもとに、現場ごとに最適な提案を行っておりますので、導入を検討されている方はぜひご相談ください。
まとめ
RFIDとNFCは、いずれも非接触型の情報取得を可能にする有効な手段であり、用途や特性によって最適な活用方法が異なります。本記事では、両者の基本的な違いに加え、周波数帯別の特徴や具体的な活用事例までご紹介しました。
導入にあたっては、技術の違いを理解するだけでなく、自社の業務フローや課題、今後の運用体制も含めて総合的に検討することが重要です。費用対効果やスケーラビリティを見極めたうえで、現場に適した仕組みを選定することで、より高い成果につながります。
高千穂交易株式会社では、70年以上に渡り培ってきた技術知見を活かし、現場診断から導入支援、保守運用まで一貫したサポートをご提供しています。RFIDやNFCの導入をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。